6/28(金)に総合学習として、薬物乱用防止教育を開催しました。大阪府こころの健康総合センターと堺市こころの健康センターから職員の方にお越しいただき、また、話の中で、実際に経験された方の体験談も交えて、薬物乱用防止に関する観点をお話しいただきました。
主なテーマとして2つの柱があり、1つは「依存症」、もう1つは「ストレス」について話していただきました。
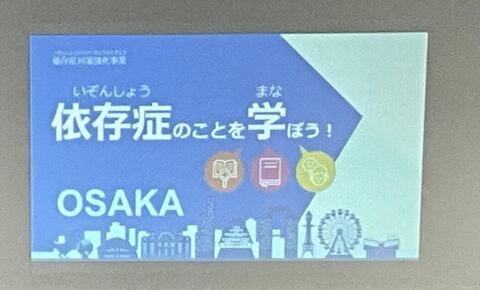
ここ数年、小中高生に関連するのがスマホ依存に関連する話でした。
小中高と学年が上がるにつれて、スマホゲームの時間が長くなる傾向にある。
すると、夜が遅くなる、課金する、家族と食事しなくなる、ゲーム等に夢中でお風呂に入らない、昼夜逆転、さらにはそれを邪魔されることで性格が荒くなることもあるなど自身の生活や人間関係もうまくいかなくなるような状況に陥る可能性が高くなるとのことでした。
ここで、ワークシートにゲームの取組み状況に関する項目について生徒は回答しました。
どんなもので依存症になるか...
酒、アルコール...未成年は脳が未完成であったり、肝臓へのダメージが大きいと言われている。
違法薬物...覚醒剤、コカイン、大麻、MDMA、LSDなどの薬物依存。
これらにより、後遺症や禁断症状、イライラしたり、落ち着きなくなるなど、回数が増えるほど依存になる可能性が大きくなるということです。
他にも、違法ではないが、医薬品や咳止め、風邪薬、痛み止めといった薬も、誤った服用をすると病気になったりいろんな問題が起こります。
最近ではオーバードーズ(OD)という言葉をよく耳にします。
市販の薬を多量に服用してしまい、命が危険になるという事象です。
ここに至るまでに、精神的なもの、人間関係など背景は様々ですが、子どもたちを取り巻く環境は厳しいものなのだと思うことがあります。
我々教職員をはじめ、周囲の大人がしっかり見守れる環境を構築することはとても大切だと感じます。
依存症は誰もが鳴る可能性を秘めているとのことです。
心や体の問題、不眠、拒食、生活時間のリズムの乱れ、家庭内問題、信用失墜、孤立なそ、きっかけは身近にあります。
依存症の方は辛い体験による心の怪我を持っている人が多いため、周囲の人のサポートも大切です。
今の時代、ITが進化しているため、画面上でなく直接対面で接する機会が減っている感じがあります。一方に偏ることなく、バランスよく行動しないといけないのではと感じることもありました。
依存症について正しい知識を理解することが大切だと感じました。
ここで、教員による芝居で違法な薬物を誘われた場合の対応について演じました。
1つは、ついつい対応してしまうパターン、もう1つは毅然と拒否するパターンです。
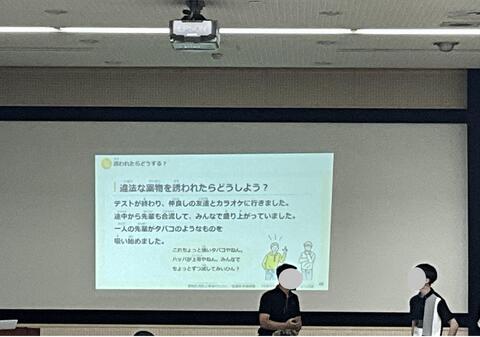
先輩など知り合いから誘われる(強要される)と断りにくいと思いますが、ダメなものはダメと毅然とした対応が必要です。今後の人生のことを考えるととても大切なことです。
後半はストレスとの付き合い方について話を伺いました。
ストレスは誰もが抱えてしまうものです。それを発散する方法が問題です。
ストレス発散方法を薬物などに頼ることがないよう早いうちに発散方法を見つけておくことが大事だと思いました。
体のサインとして、肩こり、頭痛、めまい、耳鳴り、寝つきが悪い、食欲減退、食べ過ぎ
こころのサインとして、怒りっぽい、泣きやすい、イライラ
などが現れることがあるようです。
生活習慣を整える、適度な運動でたまったエネルギーを発散したり、散歩、美味しいものを食べるなど自分に合ったものを見つけることが大切です。
最後にワークシートで自分のストレスについて考えました。
今日の講義で依存症について知識を深め、特に薬物乱用防止に関して理解を深めてくれたことと思います。
講師の皆様、ありがとうございました。